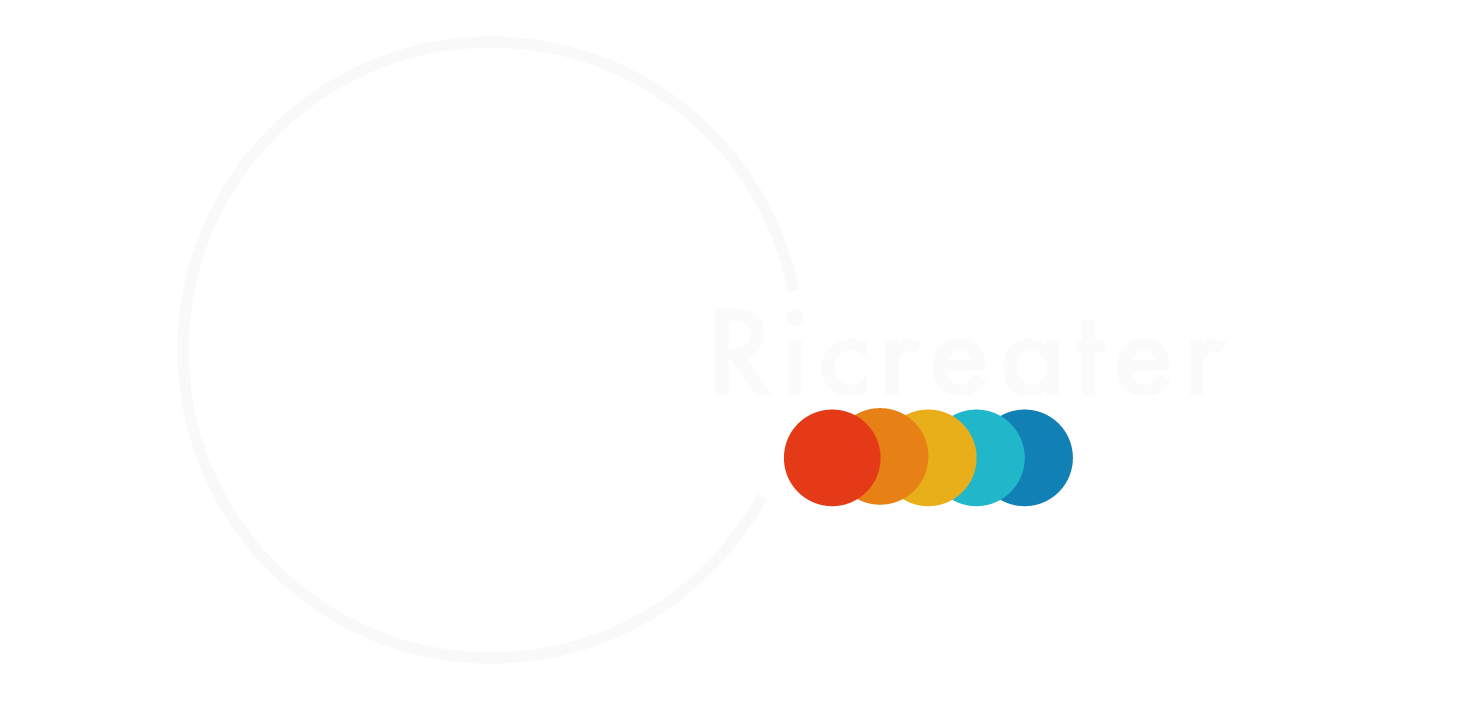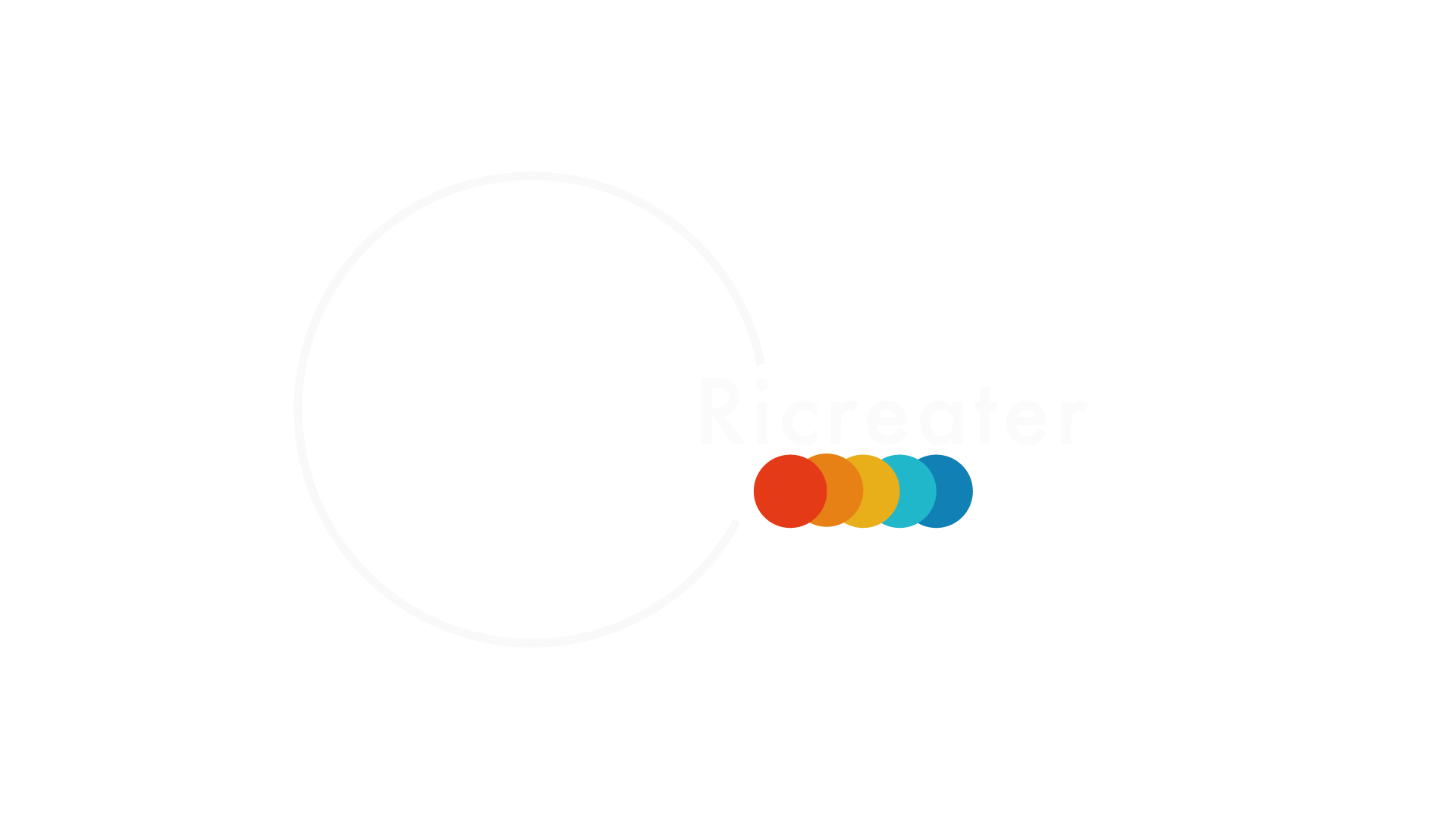動画制作を始める際に、著作権の問題は避けて通れない重要な課題です。初心者クリエイターがYouTubeやSNS用の動画を作成する際、「使ってはいけないものは何か」「許諾を得る方法は?」などの疑問を抱えている方も多いでしょう。本記事では、著作権基礎知識から具体的な注意点まで詳しく解説し、安心して動画を制作できるようサポートします。
動画制作で発生する著作権とは?基本の仕組みと定義
動画制作においては、完成した映像やその中に含まれる音楽・画像など、あらゆる表現が「著作物」として扱われます。ポイントは、これらは完成と同時に自動的に著作権が発生するという点です。つまり、著作物を登録したり届け出たりしなくても「保護対象」になるということですね。これは日本の著作権法が「無方式主義(むほうしきしゅぎ)」を採っているからこそ可能な仕組みです。
では、「動画制作 著作権」としてどのような保護が発生するかというと、大きく分けて2種類あります。一つ目は、経済的利益を保護する「著作権(ちょさくけん)」で、作品のコピー・販売・上映などをコントロールできます。もう一つは「著作者人格権(ちょさくしゃじんかくけん)」で、作者として名前を表示してもらうことや、自分の意図と異なる改変を拒否できる人格ベースの権利です。
知的財産として見た場合も、このように動画作品はいくつもの法律知識が関わります。ただ単に自分で撮ったから自由だと思い込むと、それが他人の素材だった場合には知らず知らずのうちに違法になるリスクも。特に音楽や写真素材などの場合、それぞれ別々に確認・許諾が必要になってきます。
| 著作物例 | 関連権利 | 備考 |
|---|---|---|
| 動画本体 | 著作権・著作者人格権 | 制作時に自動発生 |
| 音楽・BGM | 音源著作権 | 権利者が異なるケースあり |
| 写真・画像 | 著作権 | 素材ごとに確認が必要 |
動画制作における音楽著作権のポイントとBGM利用ルール
動画制作にBGMを使う際、「音楽ならなんでも流していい」と思っていたら大間違いです。実は、多くの音楽には「音楽著作権」が絡んでくるため、使い方を誤ると一発で違法扱いになります。
まず、動画に市販CDや配信サービスで聴いている曲を使う場合、それらはすべて「使用許可」が必要です。加えて、それがJASRACなど管理団体によって登録・管理されている曲なら、許可申請と利用料の支払いも発生します。この申請を怠ると、YouTubeでは容赦なく動画削除されたり、収益化が無効になることもあります。
特にbgm著作権関連でよくある失敗例として、「フリー素材だからOKだろう」と雑に扱うことがあります。しかし「ロイヤリティフリー」=「完全自由」ではなく、「クレジット表記が必須か」「商用利用していいか」の条件確認はマストです。素材ひとつひとつに使用条件があり、それを守らなければ契約違反と見なされてしまいます。
逆に、安全策としてオススメなのは以下のような方法:
- 著作権処理されたライセンス付き有料素材を使う
- 自分で作曲した音源(共同制作の場合は契約書で明記)
- 編集ソフトに収録されたBGM(ただし規約必読)
利用可・不可の判断リスト(BGM使用時)
- 購入CDの音楽 → 許可必要
- 配信サービスの楽曲 → 許可必要
- JASRAC管理曲 → 管理団体への申請が必要
- 商用動画での使用 → 基本的に許諾が必要
- クラシック(著作権切れ) → 原則自由
- フリー素材(利用条件付き) → 条件を遵守すればOK
- 自作音楽 → 原則自由だが共同制作時は契約記載要
- 編集ツール付属BGM → 規約確認のうえ使用可能
つまり、動画制作音楽には想像以上に繊細なbgm著作権ルールがあります。表面的な無料や公開情報だけで判断せず、「この音源著作権、本当にクリアか?」という意識こそ、安全運用の第一歩ですよ。
フリー素材や外部コンテンツを動画に使うときの著作権注意点
「フリー素材だから勝手に使って大丈夫」──そう思って動画作成している人、かなり危ないです。実際、フリー素材でも「利用条件付き」の著作物がほとんどで、自由利用どころか、ルール違反として著作権侵害の対象になることも珍しくありません。
たとえば無料BGMを使った際、「商用利用不可だった」「クレジット表記義務を守らなかった」といった理由で争いになるケースも確認されています。特にYouTubeやSNSなど公開性の高い媒体で配信する場合、一度アップロードしたあとに削除命令が来たり、最悪の場合は損害賠償請求につながる可能性すらあります。
| 素材形式 | 商用利用 | クレジット表記 |
|---|---|---|
| 無料BGMサイト | 条件付きで可 | 必須が多い |
| 有料音源サービス | 原則可 | 不要が多い |
| 写真素材サイト(無料) | 一部不可 | 必須 |
| クラシック音楽 | 可(著作権切れ) | 不要 |
| SNS投稿画像 | 原則不可 | 使用不可が原則 |
外部コンテンツを使う際には、「誰のものか」「条件は何か」を1つずつ丁寧に確認しましょう。とくにフリー素材については、自分が今制作している動画が商業利用になるのかどうか、その場合追加許諾が必要なのかという部分まで見逃せません。また、外注時にはコンテンツ利用を含めた明確な著作権契約書を交わすことも非常に重要です。曖昧なまま進めると、後からトラブル発生→損害責任という流れになりますよ。
外注・制作会社との著作権契約で気を付けるべきポイント
動画制作を制作会社に外注したとき、「完成動画は自分のもの」と思ってたら大間違いです。それ、契約内容次第ではぜんぜん自由に使えないこともあるんですよ。
例えば、納品された動画がSNSでシェアできなかったり、広告に流用できなかったり。これ全部、「著作権契約書」にどう記載されてるかにかかってます。つまり、どちらが著作権を保有するのか、それと利用条件(契約条件)や映像内素材のライセンス契約関係までキッチリ明文化しておく必要があります。
動画に使われているBGMやイラストなど外部素材にもそれぞれ個別の著作権があります。これらは「勝手に使ってませんよ」という確認と、「使用許可は誰が取ったのか」も含めて文書化しておかないと、後からトラブルになります。また、モデルや社員など出演者がいる場合は肖像権にも注意。広告転用する可能性があるなら、その段階でしっかり許諾を取っておきましょう。
契約書で確認すべき項目(6カ条)
- 発注者 or 制作会社、どちらが著作権を持つか明記
- 二次利用の可否(広告転用・SNS転載など)
- 制作に使用する素材のライセンスの所在
- クレジット表記の有無
- 素材の著作権もクリアしているか確認
- モデル・出演者の肖像権に関する使用許諾有無
このあたり事前に詰めず進行すると、「公開した瞬間違反」「再編集できない」なんてシャレにならない事態になりますからね。本当にちゃんと読もう、著作権契約書。
YouTubeをはじめとした動画公開時の著作権侵害リスクと実例
動画制作 著作権において、最も見落とされがちなポイントが「アップロード後の著作権チェック」に関するリスクです。特にYouTubeやSNSといった公開プラットフォームでは、自動検出ツールによってすぐに無断使用がバレる仕組みになっています。「ちょっとだけなら平気だろう」という感覚で映画の1シーンや有名曲をBGMに使った結果、想像以上に大きなトラブルに発展することもあります。
実際に起こりうるペナルティとしては以下のようなものがあります:
- 動画削除
- 収益化停止
- チャンネル凍結やBAN
- 数十万円〜数百万円規模の損害賠償請求
- 最悪の場合、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(刑事罰)
たとえば2018年3月には、札幌市内の理容室が店内BGM利用について音楽管理団体への使用料を支払っておらず、「3万1千円」の損害賠償を命じられました。このように個人商店であっても例外ではなく、知らず知らずのうちに法律違反となってしまうケースが多発しています。ムービー作成だけで満足せず「公開前チェック」を抜け目なく行うことが重要です。
著作権侵害となった実例5選
- 映画やテレビ番組を無断でアップロード
- CM楽曲を無断でBGMに使用
- 書籍の朗読動画を許可なく配信
- 漫画のネタバレ動画を公開
- 個人撮影の動画に有名楽曲を未許可で挿入
著作物とは「創作された表現」すべてが対象になるため、何秒使ったか・引用元を書いたかは関係ありません。万が一トラブルになった場合、法律相談なしでは対応しきれないこともあるため、最初から「権利侵害しない設計」で制作することが正解です。
肖像権と著作権の違い:撮影対象の映り込みや出演者との権利整理
動画制作 著作権というと音楽や映像の使用許可に意識が行きがちですが、「写っている人」に関する肖像権の確認も極めて重要です。肖像権とは、その人の顔や姿かたちが無断で撮影・使用されることを防ぐための「人物に関する権利」です。著作物そのものを保護する動画制作著作権とは異なり、あくまで“個人”に対して発生します。
具体的には一般人を勝手に撮って使ったり、有名人の画像を許可なく宣伝目的で使うなどは、肖像権侵害となる可能性があります。また社員インタビューやモデル起用などの場合、事前に「その映像がどこで利用されるか(SNS? CM?)」について合意を取ることで、あとから「そんな形で出るとは聞いてない」と揉めるリスクを防げます。
| 肖像権の種類 | 内容 |
| —————- | ————————————————- |
| 人格権(プライバシー) | 無断撮影されない権利、一般人に主に適用 |
| 財産権(パブリシティ) | 有名人などの肖像を広告に使う際の許諾権 |
さらに屋外撮影でも油断禁物です。通行人などがたまたま背景に映った程度であれば通常問題になりませんが、その人物が画面中央で長時間登場し鮮明な場合などは「意図的な使用」と見なされ、肖像権トラブルになるケースもあります。動画編集段階でぼかし処理するなど配慮しておくと安心です。こうした小さな配慮こそが、大きなクレームや損害賠償からあなた自身を守る「現場レベルの権利保護」になりますよ。
初心者がやりがちな著作権の誤解と避けるべき落とし穴
動画制作 著作権において、初心者が無意識にやってしまいがちな誤解って、本当に多いんですよね。特に「ちょっとだから大丈夫でしょ」とか「使った人もいたし平気だろう」みたいな感覚で進めてしまうと、知らぬ間に知的財産を侵害してしまうリスクがあります。
問題なのは、「悪意がない」=「違法じゃない」と思い込むことです。実際には、過失でも問われるケースは想像以上に多く、例えば数秒間BGMを使っただけでも、削除や賠償請求の対象になることがあります。しかもYouTubeやSNSでは自動検出システムがあるため、「指摘される前に下げればセーフ」みたいな考え方は通用しません。
よくある5つの誤解(すべて実際にはアウト)
- クレジット表記すれば使用OK → NG(許諾なしの時点でアウトです)
- 数秒の使用なら問題ない → NG(時間ではなく「無断利用」が違反)
- 他の人も使っているから安心 → NG(他人と同じ違法をしても免責にはならない)
- 訴えられたら削除すればよい → NG(損害賠償責任は残ります)
- 故意でなければ違法ではない → NG(過失でも著作権侵害は成立)
動画作成=コンテンツ発信という時代だからこそ、正しい知識を持っておかないと、「知らず知らず」に加害者になる危険性がありますよ。
動画制作 著作権に関する結論
動画制作を始めるとき、著作権についての理解が不足するとトラブルになることがあります。私は初めて動画制作に挑戦した際、どの素材を使用するのが安全なのか、正式な許諾を得るにはどんな手続きが必要なのか迷いました。しかし、著作権の基本を理解し適切なルールに従うことで、意図せずに違反行為を避けることができました。
主なポイントとしては、利用したい音楽や画像の著作権を確認し、許諾が必要な場合は確実に取ること。そしてフリー素材であっても利用規約を確認し、適切なクレジット表記や利用範囲を遵守することです。違反するリスクは大きくなくとも、万が一トラブルが発生すると時間とコストが予想以上にかかるため、事前対策は重要です。
動画制作における著作権の管理についてお伝えしたことが、あなたのクリエイティブ作業をスムーズに進める手助けになれば嬉しいです。これからも安心して創作活動に励んでください。頑張ってくださいね!